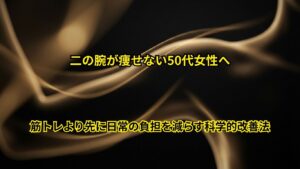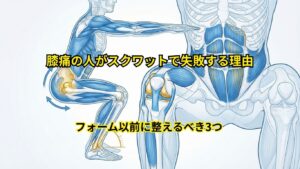目次
毎日たった10分!
階段昇降で健康寿命が9.7年延びる
【科学的ロコモ予防法】
エレベーターをやめて階段を使うだけ!調布市のパーソナルジムが教える、
初心者でも安全に始められる健康寿命延長トレーニング
なぜ今、階段昇降が注目されているのか?
「最近、階段を上がると息切れする」「膝が痛くて階段が辛い」──そんな悩みを抱えていませんか?
実は、日本人の平均寿命は女性87.74歳、男性81.64歳と世界トップクラスですが、「健康寿命」との差は約10年もあります。この差を縮めるカギとなるのが「ロコモティブシンドローム(ロコモ)の予防」です。
階段昇降は、特別な器具も場所も必要なく、日常生活の中で簡単に実践できる最高のロコモ予防トレーニング。スイス連邦工科大学の研究では、エスカレーターを階段に変えただけで最大酸素摂取量が約9%上昇し、心血管系の健康度が大幅に改善することが証明されています。
この記事で分かること
- ロコモティブシンドロームの基礎知識
- 階段昇降が健康寿命を延ばす科学的根拠
- 初心者でも安全に始められる階段トレーニング法
- レベル別トレーニングメニュー
- よくある質問と注意点
ロコモティブシンドローム(ロコモ)とは?
ロコモティブシンドローム(略称:ロコモ)とは、骨、関節、筋肉などの運動器の機能が衰えることで、「立つ」「歩く」などの移動機能が低下した状態を指します。2007年に日本整形外科学会が提唱した概念で、超高齢社会を迎えた日本における重要な健康課題です。
ロコモの三大原因疾患
骨粗鬆症
骨密度の低下により、骨折リスクが増加。特に女性は閉経後に急激に進行します。
変形性関節症
膝や股関節の軟骨がすり減り、痛みや変形が生じます。肥満も大きな要因に。
脊柱管狭窄症
背骨の神経が圧迫され、腰痛や足のしびれが発生。歩行困難につながります。
あなたは大丈夫?ロコモチェック
- 片脚立ちで靴下が履けない
- 家の中でつまずいたり、滑ったりする
- 階段を上がるのに手すりが必要
- 15分続けて歩けない
- 2kg程度の買い物袋を持って帰るのが困難
1つでも当てはまる方は、ロコモ予備軍の可能性があります。
階段昇降の驚くべき科学的効果
① 健康寿命を最大9.7年延長
2018年に『Mayo Clinic Proceedings』誌で発表された研究によると、運動習慣のある人は運動習慣のない人と比較して、平均寿命が顕著に延びることが明らかになりました。中でも階段昇降を含む日常的な運動は、健康寿命延長に極めて効果的です。
② 心血管疾患リスクを20%以上減少
米国チューレーン大学の研究では、1日に3〜5階分の階段昇降を行うだけで、心臓発作、心不全、脳卒中などの心血管疾患のリスクが20%以上減少することが示されました。わずか10分程度の階段昇降でも、心肺機能を高められ、健康効果を期待できます。
③ 下半身筋力を効率的に強化
日本の高石氏による研究では、50代の男女12人を対象に、椅子からの立ち上がり、平地歩行、階段上りの運動を比較。階段昇降は速歩よりも筋力維持・強化に効果的であることが証明されました。
階段昇降の運動強度
階段昇降:3.5メッツ(安静時の3.5倍のエネルギー消費)
平均的な建物の階段(2階まで13〜14段)を「一段飛ばし」で上ると、片脚6〜7回の自重トレーニングに相当。1日に5回階段を使えば、気づかないうちに30〜35回の自重筋トレを実行しているのと同じ効果が得られます。
④ 血糖値コントロールを改善
階段を下りる運動を続けると、耐糖能(血糖値の上昇を抑える働き)が高まるという報告があります。これは着地動作において、速筋といわれる筋肉がよく使われるためです。糖尿病予防にも効果的なトレーニング方法です。
初心者でも安全!階段トレーニングの始め方
始める前の重要な注意事項
- 医師への相談:膝や腰に痛みがある方、心臓病の既往がある方は必ず医師に相談してください
- ウォーミングアップ:軽いストレッチや準備運動を5分程度行いましょう
- 適切な靴:滑りにくく、クッション性のある運動靴を着用してください
- 水分補給:運動前後の水分補給を忘れずに
正しいフォームの基本
- 手すりを使用:特に初心者は必ず手すりを軽く握って安全を確保
- 姿勢を保つ:背筋を伸ばし、前傾姿勢にならないように注意
- 足全体で踏む:つま先だけでなく、足裏全体でしっかり踏み込む
- 膝の位置:膝がつま先より前に出ないよう意識する
- 呼吸を止めない:自然な呼吸を心がける(上りで吐く、下りで吸う)
レベル別トレーニングメニュー
運動習慣がない方・60代以上の方向け
目標:階段昇降に慣れ、安全に続けられる習慣を作る
週間スケジュール
- 第1〜2週:1日1回、2階分(約30段)をゆっくり上る(手すり使用OK)
- 第3〜4週:1日2回、2階分を上る
- 第5週以降:1日3回、3階分(約45段)に挑戦
ポイント:無理をせず、休憩を挟みながら実施。痛みを感じたら即中止。
軽い運動習慣がある方・40〜50代の方向け
目標:心肺機能と筋力を効率的に向上させる
週間スケジュール
- 第1〜2週:1日2回、5階分(約75段)を普通のペースで上る
- 第3〜4週:1日3回、5階分を上る + 下りもゆっくり意識的に
- 第5週以降:1日3回、7階分(約105段)+ 一段飛ばしを一部導入
ポイント:上りだけでなく、下りも筋トレ効果があることを意識。ゆっくり丁寧に。
運動習慣がある方・アスリート向け
目標:持久力と筋力を最大限に高める
週間スケジュール
- 月・水・金:10階分(約150段)を3セット、一段飛ばし含む
- 火・木:5階分をダッシュで2セット + ゆっくり5階分を2セット
- 土:15階分(約225段)を連続、ペース走
- 日:積極的休息(軽いストレッチ)
ポイント:インターバルトレーニングを取り入れ、心肺機能を限界まで高める。
時間がない方へ:細切れ運動のススメ
まとまった時間が取れない方は、「細切れ運動」が効果的。通勤時、買い物時、オフィスビルで──1日の中で階段を使う機会を意識的に増やすだけでOK。カナダのマックマスター大学の研究では、数分間の階段昇降を1日に何度か行うだけでも、筋肉や心臓血管の健康を改善できることが示されています。
安全に続けるための注意点
こんな時は中止してください
- 膝や腰、足首に鋭い痛みを感じた時
- めまいや吐き気、動悸が激しい時
- 階段が濡れている、暗い、手すりがない時
- 体調不良や睡眠不足の時
- 食後すぐ(最低30分は空ける)
膝を守るためのコツ
- 上りよりも下りの方が膝への負担が大きいことを意識
- 下りる時は特にゆっくりと、足裏全体で着地
- 膝のサポーターを活用(不安がある方)
- 週に1〜2日は休息日を設ける
- トレーニング後は必ずストレッチ
いつ実施するのがベスト?
朝:代謝が上がり、1日のエネルギー消費量が増加
昼:体温が高く、筋肉が動きやすい
夕方:筋力が最も発揮される時間帯
結論:ライフスタイルに合わせて継続できる時間帯が最適です。
あわせて読みたい!THE FITNESSの人気記事
【忙しい人必見】1日10分で健康維持!科学的に証明された簡単健康法 【医学的根拠あり】更年期女性が今すぐ始めるべきエストロゲン対策運動法 インナーマッスルトレーニングで体幹強化!姿勢改善とロコモ予防よくある質問(FAQ)
参考文献
-
日本老年医学会「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」
https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/publications/other/pdf/review_geriatrics_49_393.pdf -
厚生労働省研究班「エビデンスに基づいたロコモティブシンドロームの対策におけるマニュアル」
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/download_pdf/2021/202109013A.pdf -
産経新聞100歳時代プロジェクト「速歩より階段の上り下り 筋力維持」
https://100ages.sankei.com/others/news/20200220/otr2002200001-n1.html -
J-STAGE「骨粗しょう症・ロコモティブシンドロームの予防に向けた中年期からの食育」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/shokuiku/11/1/11_35/_pdf -
健康長寿ネット「ロコモティブシンドロームの予防」
https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/locomotive-syndrome/yobou.html
THE FITNESS
プロフェッショナルサポートで確実な結果を
THE FITNESSは、科学的根拠に基づいたトレーニングメソッドを提供するパーソナルジムです。プログラムをさらに深く、そして確実に実践したい方のために、パーソナライズされたサポートをご用意しています。
確実な結果をお約束
専門サポートで成功率
95%
※2024年度実績
調布市のパーソナルジム THE FITNESSでは、単なるトレーニング指導を超えて、一人ひとりのライフスタイルに合わせた継続可能なボディメイク・健康習慣をサポートします。科学的根拠と豊富な実績に基づいた確実なメソッドで、あなたの目標達成をお手伝いいたします。
今日から始める!
科学的根拠に基づいたこのプログラムは、単なる外見の改善だけでなく、健康的な身体機能の向上をもたらします。今日この瞬間から、理想の自分への第一歩を踏み出しませんか?
✨ あなたの変化が始まります ✨
継続は力なり。一日一歩の積み重ねが、理想の目標を現実にします。
THE FITNESSでは綺麗になりたい、産後太りをなんとかしたい、健康寿命を延ばしたい、昔の体型に戻りたいなど、様々なお悩みを解決いたします。
初めての方も大歓迎です。
自宅でお手軽オンラインパーソナルレッスンにも対応しています。
些細な事でもお気軽にお問い合わせください。
https://thefitness-personal.jp/contact/
070-1460-0990