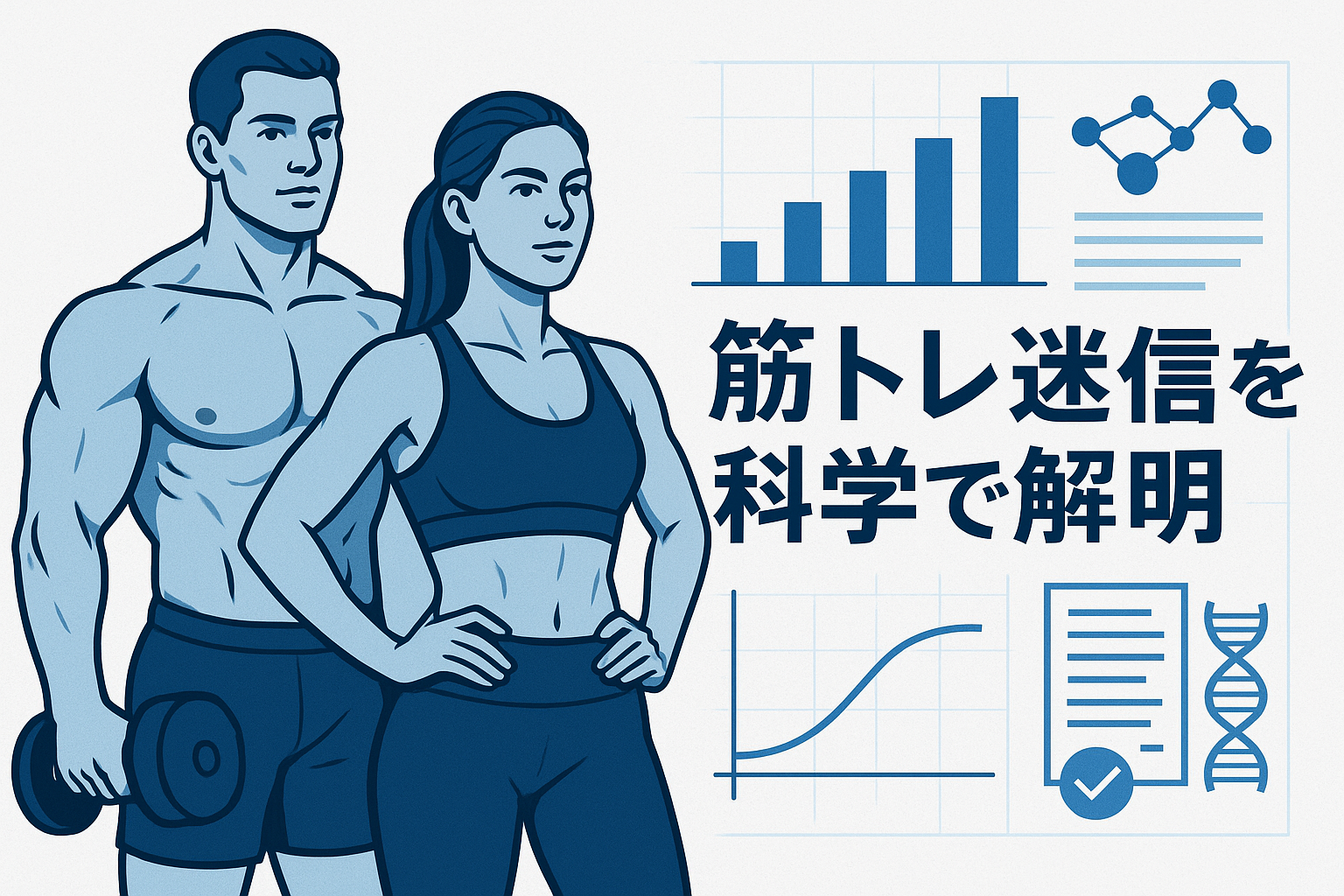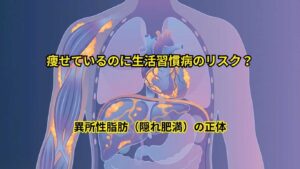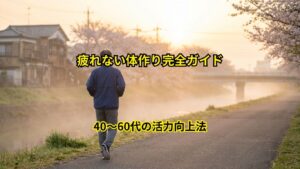目次
筋トレの10の迷信を科学的に検証
科学的根拠に基づいた効果的なトレーニング方法とは?
筋トレに関する情報は数多く存在しています。SNSやジムで耳にする「常識」が必ずしも科学的根拠に基づいているとは限りません。この記事では、広く信じられている10の筋トレの迷信を取り上げ、最新の科学的研究に基づいて検証していきます。
迷信1: 女性が筋トレするとムキムキになる?
「女性が重いウェイトを持ち上げると男性のように筋肉質になってしまう」という心配は、多くの女性が筋トレを避ける主な理由の一つです。しかし、これは科学的に根拠のない迷信です。
科学的事実:
女性と男性では、テストステロンの量に大きな差があります。テストステロンは筋肉の成長に重要なホルモンであり、男性は女性の約15〜20倍のテストステロンを自然に生成します。このホルモンの違いが、なぜ男性と女性の筋肉の成長パターンが異なるのかを説明しています。
「性別による筋力トレーニングの違い:系統的レビューとメタ分析」によれば、女性は筋力トレーニングによって筋肥大を経験するものの、その程度は男性と比較して小さいことが示されています。
参照: Roberts BM, et al. (2020). Sex Differences in Resistance Training: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Strength and Conditioning Research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33433148/
女性アスリートやボディビルダーでも、その「マッチョ」な見た目は長年にわたる極めて厳格なトレーニング、食事管理、そして場合によっては外部からのホルモン補充によって達成されるものです。一般的な筋力トレーニングプログラムでは、女性はより引き締まった体型を得ることが一般的です。
実践アドバイス:
- 女性も男性と同様に、基本的な筋力トレーニングに取り組むべきです
- 重量トレーニングは骨密度を高め、代謝を向上させ、体脂肪を減少させるのに効果的です
- 筋力トレーニングは女性の健康に多くの利点をもたらし、「マッチョ」になる心配はほとんどありません
迷信2: 乳酸が筋肉痛の原因である
「運動後の筋肉痛は乳酸の蓄積が原因である」という考えは、トレーニングの世界で広く信じられていますが、これは誤った概念です。
科学的事実:
遅発性筋肉痛(DOMS: Delayed Onset Muscle Soreness)は、運動後24〜72時間に発生する筋肉痛で、乳酸の蓄積ではなく、筋繊維の微小損傷や炎症反応によって引き起こされます。乳酸は運動後、数時間以内に体内から排出されます。
「乳酸と運動パフォーマンス:犯人か友人か?」というレビュー論文では、乳酸が筋疲労の主要な原因であるという一般的な考え方に疑問を投げかけています。実験結果は、筋肉の疲労における乳酸の役割が従来考えられていたよりもはるかに複雑であることを示しています。
参照: Cairns SP. (2006). Lactic acid and exercise performance: culprit or friend? Sports Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16573355/
1983年の研究では、被験者にトレッドミルで2種類のランニングを行わせました。乳酸濃度が大幅に増加したレベルでのランニングでは、被験者は運動後の筋肉痛をほとんど経験しませんでした。対照的に、下り坂のランニングでは乳酸の上昇は見られませんでしたが、被験者は著しい遅発性筋肉痛を経験しました。この結果は、乳酸と運動誘発性の遅発性筋肉痛の間に関連がないことを示しています。
参照: Schwane JA, et al. (1983). Is Lactic Acid Related to Delayed-Onset Muscle Soreness? The Physician and Sportsmedicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27409551/
実践アドバイス:
- 適切なウォームアップとクールダウンを行うことで、筋肉痛を軽減できます
- 徐々に運動強度を上げていくことで、急激な筋肉痛を防ぐことができます
- 乳酸を排出するための特別なマッサージや運動は、筋肉痛の軽減にはほとんど効果がありません
迷信3: 部分的に脂肪を落とすことができる(スポット減量)
「腹筋運動をたくさんすれば、お腹周りの脂肪だけを減らせる」「二の腕のエクササイズで二の腕の脂肪だけを燃焼できる」といった考え方は非常に人気がありますが、残念ながら人体はそのようにはなりません。
科学的事実:
体は全身的に脂肪を燃焼させ、特定の部位だけから脂肪を選択的に減らすことはできません。脂肪の減少は遺伝的要因によって決まる傾向があり、どの部位から最初に脂肪が減るかは個人差があります。
「スポット減量:なぜ特定の部位への減量を目指すことが神話なのか」という研究では、スポット減量の効果についての科学的証拠が一貫して否定的であることが示されています。脂肪減少は全身的に起こり、特定の部位に焦点を当てたエクササイズによってその部位の脂肪が選択的に減るわけではありません。
参照: Sydney University. (2023). Spot reduction: why targeting weight loss to a specific area is a myth. https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2023/11/07/spot-reduction–why-targeting-weight-loss-to-a-specific-area-is-.html
「スポット減量は本当に存在するのか?理論と科学的証拠についての系統的レビューとメタ分析」の研究では、既存の文献を分析した結果、局所的な運動が特定の部位の脂肪を選択的に減らすという確固たる科学的証拠はないと結論づけています。
参照: Ramírez-Campillo R, et al. (2021). A proposed model to test the hypothesis of exercise-induced localized fat reduction (spot reduction), including a systematic review with meta-analysis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34102645/
実践アドバイス:
- 全身的な脂肪減少を目指した総合的なフィットネスプログラムに取り組むことが効果的です
- 筋力トレーニングと有酸素運動を組み合わせることで、全身の脂肪燃焼を最大化できます
- 特定の部位の見た目を改善したい場合は、その部位の筋肉を鍛えることで筋肉量を増やし、全体的な体脂肪率を下げることが有効です
迷信4: トレーニング後すぐにタンパク質を摂取する「アナボリックウィンドウ」は重要
「トレーニング後30分以内にタンパク質を摂取しないと、筋肉の成長機会を逃してしまう」という考え方は、フィットネス業界で広く信じられていますが、科学的証拠はそれほど単純ではありません。
科学的事実:
トレーニング後の栄養摂取は重要ですが、「アナボリックウィンドウ」と呼ばれる特別な摂取時間は、以前考えられていたほどでもないことが研究で示されています。重要なのは、1日を通じた適切なタンパク質の総摂取量です。
「栄養タイミング再考:トレーニング後のアナボリックウィンドウは存在するのか?」という論文では、トレーニング直後の栄養摂取が筋肉の適応に不可欠であるという証拠は決定的でないと結論づけています。特にトレーニング前に適切な栄養を摂取している場合、トレーニング後の栄養摂取の厳密なタイミングはそれほど重要ではない可能性があります。
参照: Aragon AA, Schoenfeld BJ. (2013). Nutrient timing revisited: is there a post-exercise anabolic window? Journal of the International Society of Sports Nutrition. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23360586/
「タンパク質摂取のタイミングが筋力と筋肥大に与える影響:メタ分析」の研究では、トレーニングの前後のタンパク質摂取と筋肉の適応の関係を調査しました。結果は、タンパク質摂取のタイミングよりも、1日を通じた総タンパク質摂取量の方が筋肉の発達に重要であることを示しています。
参照: Schoenfeld BJ, et al. (2013). The effect of protein timing on muscle strength and hypertrophy: a meta-analysis. Journal of the International Society of Sports Nutrition. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24299050/
実践アドバイス:
- トレーニング後にタンパク質を摂取することは有益ですが、30分以内に摂取しなければならないという厳密なルールはありません
- トレーニング前に適切な食事をしていれば、トレーニング後の栄養摂取のタイミングはさほど重要ではありません
- 1日を通じて体重1kgあたり1.6~2.2gの良質なタンパク質を摂取し、3~4時間おきに均等に分配することを目指しましょう
迷信5: 有酸素運動は筋肉増強の妨げになる
「筋肉を増やしたいなら有酸素運動はやめるべきだ」「カーディオは筋肉の成長を殺す(カーディオ・キルズ・ゲインズ)」という考え方が根強くありますが、科学的証拠はもっと複雑です。
科学的事実:
適度な量と強度の有酸素運動は、筋肥大を妨げるどころか、回復を促進し、全体的な健康と体組成を改善することで、筋力トレーニングの効果を高める可能性があります。過度な有酸素運動のみが筋肉の成長に干渉する可能性があります。
「同時トレーニング:有酸素運動と筋力トレーニングの干渉効果に関するメタ分析」の研究では、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせた場合の効果を分析しました。結果は、適度な量と強度の有酸素運動は筋力や筋肥大に大きな悪影響を与えず、むしろ多くの場合、相乗効果がある可能性を示しています。
参照: Wilson JM, et al. (2012). Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. Journal of Strength and Conditioning Research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22002517/
ペロトンのブログ記事「カーディオは本当に筋肉の成長を殺すのか?」では、最近の研究が逆の可能性を示していると述べています:カーディオは筋肉の成長を妨げるどころか、むしろそれを助ける可能性があります。「近年の研究では、同時トレーニングは筋力トレーニング後の筋肥大を妨げないだけでなく、むしろ促進する可能性があることが示されています。」
参照: Peloton Blog. (2024). Does Cardio Actually Kill Your Muscle Gains? https://www.onepeloton.com/blog/does-cardio-kill-gains/
実践アドバイス:
- 筋力トレーニングと有酸素運動を別々のセッションで行うか、筋力トレーニング後に有酸素運動を行うことを検討しましょう
- 筋肉増強を主な目標とする場合は、週に2~3回の低~中強度の有酸素運動(20~30分程度)に制限しましょう
- 有酸素能力と筋肉量の両方を向上させたい場合は、HIIT(高強度インターバルトレーニング)を取り入れると効果的です
迷信6: 高齢者には筋トレは危険である
「高齢者は筋力トレーニングを避けるべきで、軽い有酸素運動だけをすべき」という考えは、今でも広く信じられていますが、科学的証拠はこの考えを強く否定しています。
科学的事実:
適切に設計された筋力トレーニングプログラムは、高齢者にとって安全であるだけでなく、筋力、骨密度、バランス、および全体的な機能を改善するために不可欠です。筋力トレーニングは、高齢者の転倒リスクを減らし、健康な生活を維持するのに役立ちます。
「高齢者のための抵抗トレーニングに関する立場声明」では、科学的研究と臨床経験の両方から、筋力トレーニングが健康な高齢者と虚弱な高齢者の両方にとって安全であることが示されています。適切な指導と段階的な進行を伴う筋力トレーニングは、高齢者の健康とウェルビーイングに多くの利点をもたらします。
参照: Fragala MS, et al. (2019). Resistance Training for Older Adults: Position Statement From the National Strength and Conditioning Association. Journal of Strength and Conditioning Research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31343601/
「重度の筋力トレーニングは高齢者の筋肥大と同様に神経筋適応を促進する」という研究では、高強度の筋力トレーニングが高齢者の筋肉量、筋力、および機能的能力を大幅に改善できることが示されました。さらに、適切な高強度トレーニングは、虚弱で病気の高齢者でも安全に実施できることがわかりました。
参照: Heavy Strength Training in Older Adults: Implications for Health and Performance. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38635392/
実践アドバイス:
- 高齢者は、専門家の指導のもとで筋力トレーニングを始めることが理想的です
- 低重量から始め、徐々に負荷を増やし、適切なフォームに集中しましょう
- 週に2~3回の筋力トレーニングセッションを目指し、主要な筋肉グループをすべて鍛えましょう
- 既存の健康問題がある場合は、トレーニングプログラムを開始する前に医師に相談することをお勧めします
迷信7: サプリメントは筋肉増強に不可欠である
「本格的な筋力トレーニングをするなら、プロテインパウダーやその他のサプリメントは必須だ」という考え方は、サプリメント業界によって強く推進されていますが、科学的事実は違います。
科学的事実:
バランスの取れた食事から十分な栄養を摂取できる場合、ほとんどのサプリメントは不要です。一部のサプリメント(特にプロテインとクレアチン)には科学的根拠があるものの、多くのサプリメントは効果が証明されておらず、中には潜在的な副作用を持つものもあります。
「筋肉量と筋力への影響が主張されているサプリメント」というレビュー論文では、人気のあるさまざまなサプリメントの有効性が評価されました。結論として、テストされたサプリメントの中で、硝酸塩とカフェインは筋力への急性的な有益な効果を示す十分な証拠があり、クレアチンとタンパク質は長期的に筋肉量と筋力の増加または維持に一貫して効果があることがわかりました。しかし、他の多くの人気サプリメントについては、効果を支持する証拠はほとんどありませんでした。
参照: Valenzuela PL, et al. (2019). Supplements with purported effects on muscle mass and strength. European Journal of Nutrition. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30604177/
「レジスタンストレーニングによる筋肉量と筋力の増加に対するタンパク質補給の効果に関する系統的レビュー、メタ分析、およびメタ回帰」の研究では、タンパク質サプリメントが筋力トレーニングと組み合わせた場合に筋肉量と筋力の増加を促進できることが示されています。しかし、効果は限定的であり、すでに食事から十分なタンパク質を摂取している人ではさらに小さくなります。
参照: Morton RW, et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. British Journal of Sports Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698222/
実践アドバイス:
- まずは食事から十分な栄養(特にタンパク質)を摂取することに重要視しましょう
- 科学的根拠があるサプリメントを検討する場合:
- ホエイプロテイン:食事からのタンパク質摂取が難しい場合に便利
- クレアチン:筋力と筋肉量の増加に効果的であることが科学的に証明されている
- 他のほとんどのサプリメントは、効果が証明されておらず、高価で場合によっては安全でない可能性があります
迷信8: 筋トレには「痛み」が必要である(No Pain, No Gain)
「痛みがなければ、効果もない(No Pain, No Gain)」という格言はジムで頻繁に聞かれますが、この考え方は誤解を招き、危険です。
科学的事実:
効果的な筋力トレーニングでは、筋肉に負荷をかけて疲労させる必要がありますが、これは必ずしも痛みを伴うわけではありません。実際、鋭い痛みや関節の痛みは怪我の兆候である可能性があり、無視すべきではありません。適度な不快感(「燃える感じ」)は正常ですが、痛みは効果的なトレーニングの必須条件ではありません。
「12の一般的なフィットネス迷信 – 反証」というレビューでは、「痛みがなければ、効果もない」の迷信について言及しています。痛みを進歩の印と見なす一般的な考えは、怪我や過剰トレーニングにつながる可能性があります。適度な不快感は正常ですが、痛みは危険信号であり、軽視すべきではありません。
参照: Avisena Specialist Hospital. (2024). 12 Common Fitness Myths – Debunked. https://shahalam.avisena.com.my/articles/12-common-fitness-myths-debunked/
「トレーニング中の疲労と痛みの管理:生理学的アプローチ」の研究では、効果的なトレーニングには疲労感が伴いますが、激しい痛みは筋肉や関節の損傷を示している可能性があることが示されています。研究者たちは、痛みと適切な疲労感の違いを認識することの重要性を強調しています。
参照: American College of Sports Medicine. (2018). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29595409/
実践アドバイス:
- 筋肉の「燃える感じ」や疲労感は正常ですが、鋭い痛みや関節の痛みは警告信号です
- 適切なフォームと適度な負荷に集中し、過度に自分を追い込むことを避けましょう
- 徐々に強度を上げ、体に適応する時間を与えることで、怪我のリスクを最小限に抑えられます
- 痛みが続く場合は、トレーニングを中断し、必要に応じて医療専門家に相談しましょう
迷信9: 週に1回の高強度トレーニングで十分
「時間がないから週1回の高強度トレーニングだけでも効果がある」という考え方は、時間効率を重視する現代社会で魅力的ですが、科学的証拠は否定しています。
科学的事実:
筋肉の成長と筋力の向上には、適切な頻度のトレーニングが必要です。研究によれば、筋肉グループごとに週に少なくとも2回のトレーニングが最適な結果をもたらします。週1回のトレーニングでも一定の効果はありますが、週に複数回トレーニングすることで、より大きな筋肥大と筋力の向上が期待できます。
「筋力トレーニングの頻度が筋肥大に及ぼす影響:系統的レビューとメタ分析」の研究では、同じ筋肉グループを週に2回以上トレーニングすることで、週に1回だけトレーニングする場合と比較して、筋肉の成長が大幅に増加することが示されました。
参照: Schoenfeld BJ, et al. (2016). Effects of Resistance Training Frequency on Measures of Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27102172/
「トレーニング頻度が筋力に及ぼす影響:メタ分析」の研究では、週に複数回のトレーニングが、週に1回だけのトレーニングと比較して、筋力の増加に対してより大きな効果をもたらすことが示されました。これは特に初心者とトレーニング経験者の両方に当てはまります。
参照: Ralston GW, et al. (2018). The Effect of Weekly Set Volume on Strength Gain: A Meta-Analysis. Sports Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29299878/
実践アドバイス:
- 最適な結果を得るためには、各筋肉グループを週に2~3回トレーニングすることを目指しましょう
- 時間が限られている場合は、全身トレーニングのルーティンを週に2~3回実施するという方法が効果的です
- 本当に週に1回しかトレーニングできない場合は、複合運動(スクワット、デッドリフト、ベンチプレスなど)を中心にして、最大の効果を得られるようにしましょう
- トレーニングの頻度よりも一貫性が重要です。長期間にわたって続けられるルーティンを見つけましょう
迷信10: 筋トレは心臓に負担をかける
「筋力トレーニングは心臓に過度の負担をかけ、特に高齢者や心臓病のリスクがある人には危険である」という考え方は、未だに根強く残っていますが、科学的証拠は支持していません。
科学的事実:
適切に実施される筋力トレーニングは、心臓に危険をもたらすどころか、心臓血管系の健康に多くの利点をもたらします。筋力トレーニングは血圧の管理を改善し、心臓病のリスク要因を減少させ、全体的な心臓血管系の健康を向上させることができます。
「心臓血管疾患の有無にかかわらず個人における抵抗運動:利点、根拠、安全性、および処方」という米国心臓協会(American Heart Association)のアドバイザリーでは、適切に処方された筋力トレーニングが心臓血管系の健康に多くの利点をもたらし、多くの心臓病患者にとって安全であると結論づけています。
参照: Pollock ML, et al. (2000). Resistance Exercise in Individuals With and Without Cardiovascular Disease: Benefits, Rationale, Safety, and Prescription. Circulation. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10683360/
「筋力トレーニングと心臓の健康:新たな視点」というレビューでは、適度な強度の筋力トレーニングが血圧を下げ、インスリン感受性を向上させ、体脂肪を減少させ、心臓病のリスクを全体的に減少させることができると結論づけています。
参照: Hurley BF, Roth SM. (2000). Strength training in the elderly: effects on risk factors for age-related diseases. Sports Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10999919/
実践アドバイス:
- 心臓病の既往歴がある場合は、筋力トレーニングプログラムを開始する前に医師の許可を得ましょう
- 適切な技術と呼吸法に焦点を当て、持ち上げている間に息を止めること(バルサルバ効果)を避けましょう
- 軽い負荷から始め、徐々に重量と強度を増やしていくことで、心臓系への急激な負荷を避けることができます
- バランスの取れたフィットネスプログラムには、筋力トレーニングと有酸素運動の両方を含めることが理想的です
まとめ:科学的根拠に基づいた効果的なトレーニング
これまでに検証してきた10の迷信からわかるように、フィットネスの世界には誤解や不正確な情報が多く存在します。科学的な視点から見ると、効果的なトレーニングのアプローチは以下のようになります:
効果的なトレーニングの科学的原則
- 筋力トレーニングは性別や年齢に関係なく、すべての人に有益です
- 適切なフォームと段階的な負荷の増加に焦点を当てましょう
- 痛みと適度な不快感の違いを理解し、怪我のサインを無視しないでください
- 栄養は重要ですが、タイミングよりも1日の総摂取量に焦点を当てましょう
- 筋力トレーニングと有酸素運動を組み合わせることで、最適な健康と体組成の結果が得られます
- サプリメントに過度に依存せず、まずは食事からの栄養摂取を最適化しましょう
- 継続性と一貫性が、どんなトレーニングプログラムでも成功の鍵です
科学的根拠に基づいたトレーニングアプローチを採用することで、より効果的に目標を達成し、怪我のリスクを減らし、長期的な健康とウェルビーイングを促進することができます。特定のトレーニングプログラムや栄養アドバイスを検討する際は、常に科学的根拠を探し、資格のあるフィットネス専門家からのアドバイスを求めることをお勧めします。
※個人の健康状態や目標によって、最適なアプローチは異なります。新しいトレーニングプログラムを開始する前に、医療専門家に相談することをお勧めします。
参考文献
1. Roberts BM, et al. (2020). Sex Differences in Resistance Training: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Strength and Conditioning Research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33433148/
2. Cairns SP. (2006). Lactic acid and exercise performance: culprit or friend? Sports Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16573355/
3. Schwane JA, et al. (1983). Is Lactic Acid Related to Delayed-Onset Muscle Soreness? The Physician and Sportsmedicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27409551/
4. Ramírez-Campillo R, et al. (2021). A proposed model to test the hypothesis of exercise-induced localized fat reduction (spot reduction), including a systematic review with meta-analysis. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34102645/
5. Aragon AA, Schoenfeld BJ. (2013). Nutrient timing revisited: is there a post-exercise anabolic window? Journal of the International Society of Sports Nutrition. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23360586/
6. Schoenfeld BJ, et al. (2013). The effect of protein timing on muscle strength and hypertrophy: a meta-analysis. Journal of the International Society of Sports Nutrition. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24299050/
7. Wilson JM, et al. (2012). Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. Journal of Strength and Conditioning Research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22002517/
8. Fragala MS, et al. (2019). Resistance Training for Older Adults: Position Statement From the National Strength and Conditioning Association. Journal of Strength and Conditioning Research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31343601/
9. Valenzuela PL, et al. (2019). Supplements with purported effects on muscle mass and strength. European Journal of Nutrition. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30604177/
10. Morton RW, et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. British Journal of Sports Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698222/
11. Schoenfeld BJ, et al. (2016). Effects of Resistance Training Frequency on Measures of Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27102172/
12. Pollock ML, et al. (2000). Resistance Exercise in Individuals With and Without Cardiovascular Disease: Benefits, Rationale, Safety, and Prescription. Circulation. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10683360/
13. Hurley BF, Roth SM. (2000). Strength training in the elderly: effects on risk factors for age-related diseases. Sports Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10999919/
THE FITNESSでは綺麗になりたい、産後太りをなんとかしたい、健康寿命を延ばしたい、昔の体型に戻りたいなど、様々なお悩みを解決いたします。
初めての方も大歓迎です。
自宅でお手軽オンラインパーソナルレッスンにも対応しています。
些細な事でもお気軽にお問い合わせください。
https://thefitness-personal.jp/contact/
070-1460-0990